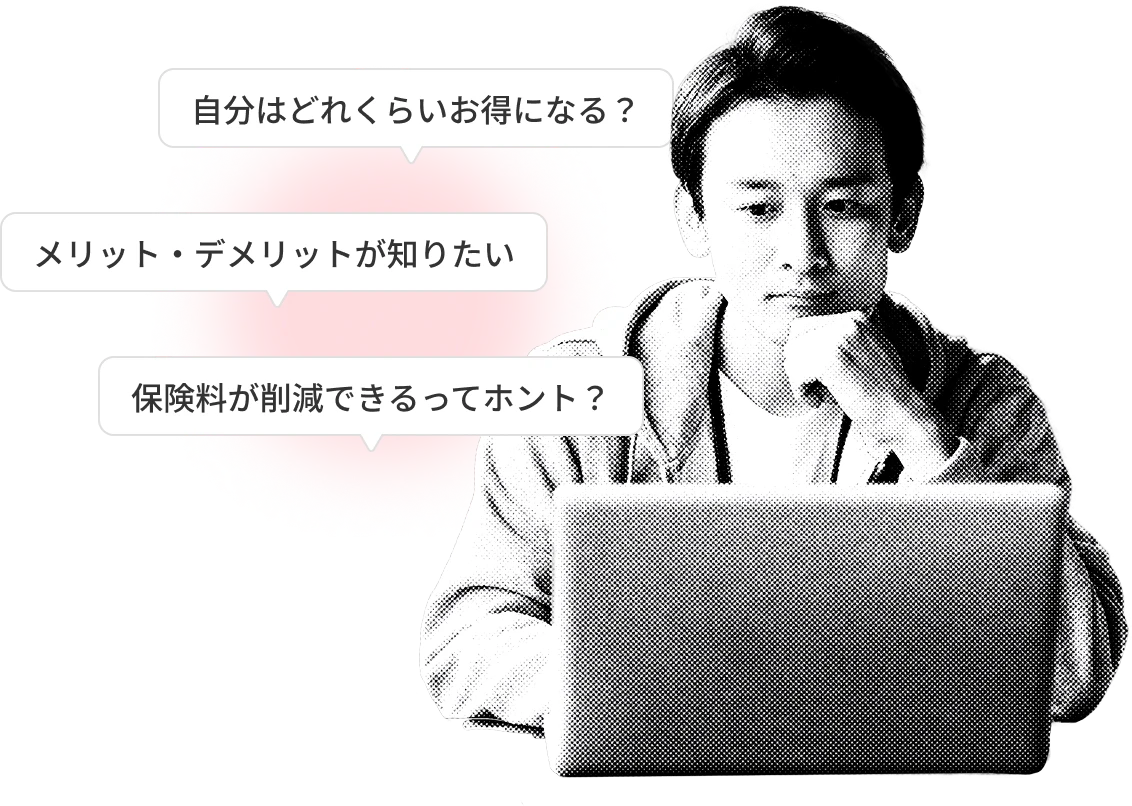- 社会保険・年金
フリーランスの国民健康保険の入り方|手続きは14日以内に!

フリーランスとして働き始めたばかりの方にとって、まず直面するのが「健康保険の切り替え」です。多くの方が国民健康保険を選択しますが、退職日の翌日から14日以内に加入手続きをしないと、医療費が全額自己負担になるリスクもあります。
本記事では、フリーランスの国民健康保険の入り方について、いつ・どこで・何をすればよいのかを具体的に解説します。初めての方でも迷わず手続きできるよう、流れと必要書類をわかりやすくまとめました。
フリーランスになったらまず確認!国民健康保険の入り方とその重要性
フリーランスになると、会社の健康保険から自動的に脱退します。これにより健康保険証が無効となり、放っておくと「無保険状態」に。無保険のまま医療機関を受診すると、費用は全額自己負担、つまり10割負担となります。
このリスクを避けるため、多くの方が選ぶのが「国民健康保険」への加入です。これは住民票のある市区町村が運営する保険制度で、自営業者やフリーランスの多くが加入しています。健康保険を切らさないためにも、退職後すぐに動き出すことが肝心です。
加入期限は14日以内!フリーランスの国民健康保険の入り方
万が一手続きが遅れたり、加入を忘れたりした場合、未加入期間中の医療費は全額自己負担となります。また、あとから加入しても、その期間にさかのぼって保険料を請求されるうえ、納付が遅れると延滞金が発生することもあります。
さらに、確定申告の際に必要な「年間保険料額の証明書」も提出できず、控除を受け損ねるリスクも。こうしたトラブルを防ぐためにも、退職後は速やかに手続きを行いましょう。
どこで手続きをする?国民健康保険の加入窓口
国民健康保険の加入手続きは、住民票のある市区町村の役所で行います。担当窓口は「国保年金課」や「保険年金課」などで、受付時間は平日8:30〜17:15が一般的です。
自治体によってはオンライン申請や郵送による対応を行っている場合や、週末に開庁している場合もあるので確認してみましょう。
国民健康保険に加入するのに必要な書類

国民健康保険に加入する際は、必要書類がきちんとそろっていないと手続きができません。窓口でのやり取りをスムーズに進めるためにも、事前の準備が大切です。
手続きに必要な持ち物リスト
以下の書類は、ほとんどの自治体で共通して必要とされる基本的な持ち物です。漏れがないかチェックしてから窓口へ向かいましょう。
- 退職日が確認できる書類
退職証明書、離職票、または健康保険資格喪失証明書など。
- 本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、顔写真付きの公的身分証明書。
- マイナンバーが確認できる書類
マイナンバーカードまたは通知カード。写しではなく原本を求められることが多いです。
- 印鑑(認印)
署名で代用可能な自治体もありますが、念のため持参しましょう。
- 世帯主に関する情報
世帯主が本人でない場合、氏名・生年月日・続柄などの情報が必要です。
※自治体によっては、口座振替依頼書や所得申告書の提出を求められることがあります。事前に各自治体の公式サイトや電話窓口で確認しておきましょう。
国保の保険料は高すぎる?フリーランスが知っておきたい計算ルール
フリーランスになって国民健康保険に切り替えると、「保険料が思ったより高い」と感じる方が多くいます。その主な理由は次の3つです:
- 保険料が全額自己負担になる
会社員時代は保険料の半分を会社が負担していましたが、フリーランスは全額を自分で支払う必要があります。
- 前年の所得をもとに保険料が決まる
現在の収入が下がっていても、会社員時代の高い所得をもとに計算されるため、実態に見合わない保険料になることがあります。
- 扶養制度がないため家族分も加算される
国保には「扶養」の概念がなく、家族全員がそれぞれ加入者となるため、人数が多いほど保険料も増えます。
年収や家族構成に応じた実際の保険料については、別記事「○○○○○○」でご紹介していますので、あわせてご覧ください。
保険証はいつ届く?手続き後すぐに医療機関に行きたいときは?
手続きが完了すると、正式な国民健康保険証は1〜2週間後に自宅へ郵送されます。申請直後に医療機関を受診したい場合は、窓口で「資格証明書(仮の保険証)」を発行してもらうことができます。これを提示すれば、当日から保険適用で受診が可能です。
仮証明書を発行しない自治体もありますが、その場合でも以下の対応で費用を取り戻せます。
- 受診時の領収書を必ず保管する
- 後日、保険証が届いてから窓口または保険者へ申請する
- 保険適用差額分の返金を受ける
このように、手続き直後に医療を受ける際は少し注意が必要です。安心して受診するためにも、申請時に保険証の発行時期や対応方法をあらかじめ確認しておきましょう。
ほかの選択肢もある!任意継続・扶養・国保組合との比較
会社を辞めたあとの健康保険といえば国民健康保険が一般的ですが、ほかにも選べる制度があります。保険料や保障内容、加入条件は制度によって異なるため、ご自身に合った選択をすることが重要です。ここでは、退職後にフリーランスとして働く方が選択できる3つの制度を紹介します。
任意継続被保険者制度
これまで加入していた会社の健康保険を、退職後も最長2年間継続できる制度です。保険料は全額自己負担になりますが、在職中と同じ保障が受けられるのが特徴です。
- 保険料は在職中の標準報酬月額に基づいて計算
- 保障内容は会社員時代と同等
- 扶養家族がいると国民健康保険より安くなる場合も
- 退職日の翌日から20日以内に申請が必要
収入が多い方や医療保障を重視したい方、扶養家族がいる方にとって有利な選択肢です。別記事「○○○○○○」で詳しくご紹介していますので、あわせてご確認ください。
出典:全国健康保険協会|健康保険任意継続制度(退職後の健康保険)について
家族の扶養に入る
収入が少ない方は、配偶者や親の健康保険の扶養に入るという方法もあります。保険料を個人で負担する必要がないため、コスト面でのメリットが大きい制度です。
加入の主な条件は次のとおりです:
- 年収130万円未満(60歳以上または障がい者は180万円未満)
- 就労実態や今後の収入見込みによっては不可
- 健康保険組合の審査がある
扶養に入れるかどうかは審査次第のため、早めに家族の勤務先の保険組合に相談しておくと安心です。
国民健康保険組合(国保組合)
特定の業種に従事する方向けに設けられた制度で、通常の国民健康保険とは異なる保険料体系や給付内容となっているのが特徴です。
特徴は以下のとおりです:
- 保険料が所得に関係なく一律の組合が多い
- 加入には組合の審査や職業証明書が必要
- 組合ごとに条件・手続き・保障内容が異なる
たとえば以下のような組合があります:
- 文芸美術国民健康保険組合
対象:文筆業・美術業・翻訳・校正・編集など
ご自身の職業に対応した組合があるかを調べておくと、選択肢の幅が広がります。別記事「知らなきゃ損!「国民健康保険」と「国民健康保険組合」の違い|選び方完全ガイド」で詳しくご紹介していますので、あわせてご確認ください。
制度の簡易比較表
制度名 | 加入期限 | 保険料の特徴 | 特徴 |
|---|---|---|---|
国民健康保険 | 退職翌日から14日以内 | 所得によって変動 | 自営業・フリーランスの基本制度 |
任意継続保険 | 退職翌日から20日以内 | 標準報酬月額ベース | 給付が手厚く、扶養家族や収入によっては割安になる |
扶養に入る | 条件を満たせば随時 | 保険料負担なし | 収入が少ない人におすすめ |
国民健康保険組合 | 組合により異なる | 一律 | 業種限定、加入条件あり |
まとめ|フリーランスの第一歩は国民健康保険の「入り方」を知ることから
退職後すぐに必要となる国民健康保険の手続きは、「14日以内」という期限さえ押さえておけば、特別むずかしいものではありません。必要書類をそろえ、住民票のある自治体の窓口で手続きをすれば、保険証を得られ安心して医療を受ける体制が整います。
保険料が高いと感じる方も、実際の計算方法や軽減制度、さらには任意継続や扶養、国保組合といった複数の選択肢を知ることでご自身に合った制度が見えてきます。
不安なままにせず、まずは「今できること」から始めてみましょう。