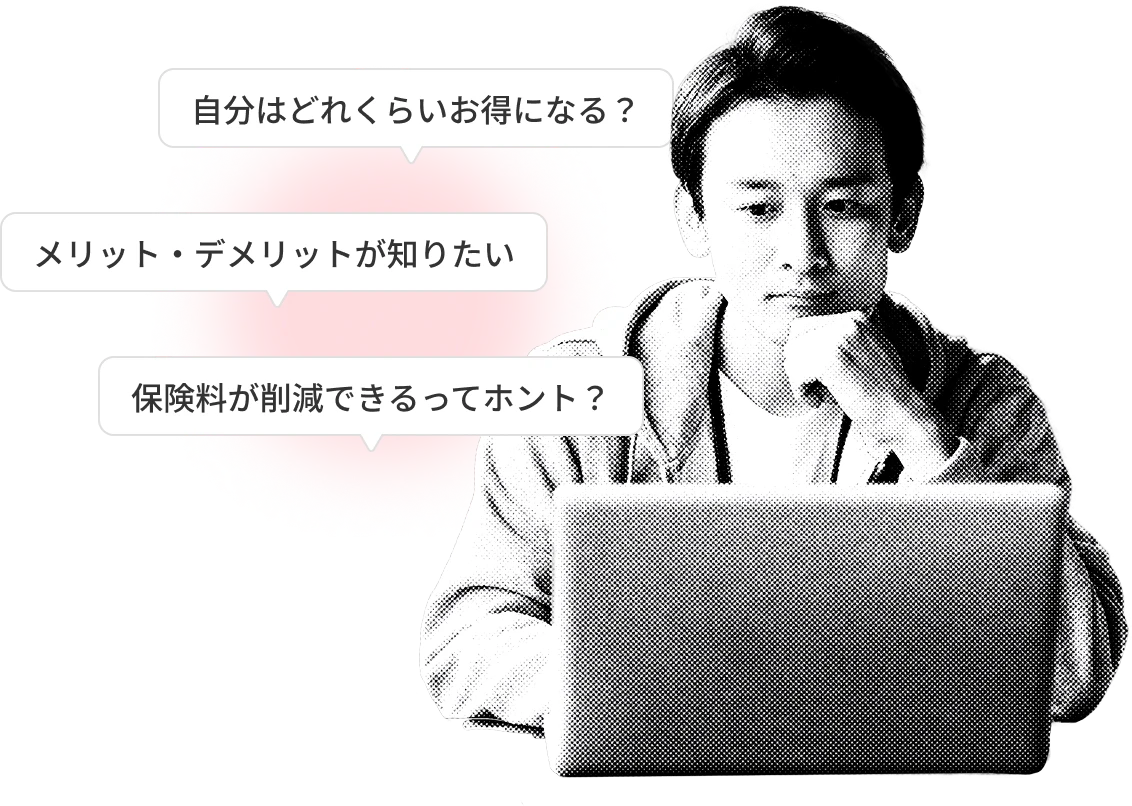- 社会保険・年金
フリーランスの社会保険料、いくらかかる?負担を抑える制度も紹介

収入が増えても手取りが少ないのはなぜ?フリーランスの保険料のリアル
会社員を辞めてフリーランスになると、真っ先に驚くのが保険料の高さです。毎月の金額を見て、「これ本当に合ってる?」と目を疑った方も多いのではないでしょうか。収入が増えても、手元に残るお金は少ない。そんな悩みの背景には、社会保険料の仕組みがあります。
この記事では、フリーランスが支払う社会保険料(国民健康保険・国民年金)の計算方法や年収別の実例を交えて、負担の全体像を整理します。その上で、合法的に保険料を軽減する制度も紹介。複雑な制度の中で、損をしない選択をするためのヒントをお届けします。
フリーランスの社会保険とは?会社員との違い
会社員とフリーランスでは、加入する社会保険の種類や保険料の負担の仕組みが大きく異なります。独立してから「こんなに払うの?」と驚く方が多いのも、この違いが理由です。
会社員の場合(厚生年金・健康保険)
- 保険料は企業と従業員で折半
- 保険料は給与から自動で天引き、手続き不要
- 健康保険は企業ごとに異なり、「協会けんぽ」や「組合健保」に加入
- 年金は「国民年金(基礎年金)」+「厚生年金」の2階建て構造
- 厚生年金には報酬に応じた上乗せ部分があり、将来の受給額が多くなる
フリーランスの場合(国民年金・国民健康保険)
- 保険料は全額自己負担
- 支払いは自分で管理
- 健康保険は住んでいる自治体の国民健康保険に加入
- 年金は基礎年金のみで、受給額は会社員より少なめ
- 扶養制度がないため、家族一人ひとりが被保険者となり、その分保険料が加算
- 所得が増えると保険料も増加
たとえば、会社員時代に月3万円の天引きだった社会保険料が、独立後は月5〜6万円を全額自己負担することもあります。企業の補助や扶養制度がなく、家族分もすべて自己負担になる点が、フリーランスの大きな負担要因です。
出典:厚生労働省「社会保障とは何か」、日本年金機構「公的年金制度の種類と加入制度」
年収別シミュレーション|フリーランスの社会保険料はいくら?

ここでは、社会保険料について詳しく見ていきましょう。
年収300万円でもこんなに?意外と高い社会保険料の現実
東京都江戸川区在住・単身フリーランス(35歳)、年収300万円(経費100万円、課税所得200万円)の場合、
- 国民健康保険:約25万円/年
- 国民年金:約21万円/年 (17,510円/月)
- 合計:約46万円(約3.8万円/月)
家族がいるとどうなる?年収500万円・家族持ちのケース
同じく東京都江戸川区在住(35歳)で、配偶者(パートで社会保険加入・35歳)と子ども2人(7歳、5歳)がいるフリーランスの場合(年収500万円、経費150万円、課税所得350万円)、
- 国民健康保険:約46万円/年(子ども2人分含む)
- 国民年金:約21万円/年(本人のみ)
- 家族分の健康保険料が加算され、合計約67万円(約5.5万円/月)
保険料だけで毎月約5.5万円となり、家計への影響は大きくなります。
年収700万円でも変わる?地方暮らしの保険料
静岡県静岡市在住・単身フリーランス(35歳)で、年収700万円(経費200万円、課税所得500万円)の場合、
- 国民健康保険:約46万円/年
- 国民年金:約21万円/年
- 合計:約67万円/年(約5.5万円/月)
都市部と比べ保険料が安くなる傾向はあるものの、所得が上がると支払額も大きくなり、負担感は増していきます。
出典:江戸川区「江戸川区国民健康保険料シミュレーション」、日本年金機構「国民年金保険料」、静岡市「令和7年度静岡市国民健康保険料自動計算ページ」
国民健康保険料を抑える3つの合法的な方法
①国保組合という選択肢|保険料が一律で管理しやすいのがメリット
一部のフリーランスは、業種ごとに設けられた「国民健康保険組合(以下、国保組合)」に加入できます。たとえば、ライターやデザイナーなどが対象の「文芸美術国保」では、保険料が所得に関係なく一律なのが特徴です。
文芸美術国保の2025年度保険料
- 組合員本人:月25,700円
- 家族1人あたり:月15,400円
- 介護保険料(該当者:40〜64歳):月6,100円
市区町村の国民健康保険では、所得によって保険料が変動しますが、国保組合は年度内は金額が一律です。そのため収支の見通しが立てやすく、収入の高い方には有利になることがあります。
国民健康保険と国保組合の違いは、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
知らなきゃ損!「国民健康保険」と「国民健康保険組合」の違い|選び方完全ガイド
出典:文芸美術国民健康保険組合「保険料について」
②扶養に入るという選択肢|条件を満たせばゼロ円も可能
配偶者が会社員や公務員で健康保険に加入している場合、一定の条件を満たせば扶養に入ることが可能です。扶養に入ると保険料は発生せず、以下のようなメリットがあります。
- 本人の保険料負担がゼロ円に
- 所得が少ない時期の支出を大きく軽減
特に開業初期や事業が軌道に乗るまでの間は、有効な選択肢となります。扶養に入るには収入基準などの確認が必要なので、配偶者が加入している健康保険組合に相談するのが安心です。
出典:全国健康保険協会「被扶養者とは?」
③どうしても払えないときは?免除・猶予制度を賢く使う
国民年金には、保険料の支払いが難しいときに活用できる「免除制度」と「納付猶予制度」があります。前年または前々年の所得が一定額以下、または失業中の場合などに申請でき、承認されると納付の負担が軽減されます。
- 免除制度:全額・4分の3・半額・4分の1の4段階で免除
- 納付猶予制度:20歳以上50歳未満が対象。本人と配偶者の所得基準で判断
申請できるのは、過去2年1カ月以内の保険料分まで。免除期間中も将来の年金の受給資格にカウントされ、障害年金や遺族年金の対象にもなります。未納では受け取れない保障もあるため、払えないときは放置せず、必ず手続きを行いましょう。
出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
社会保険と節税の関係|仕組みを知れば手取りが変わる
社会保険料の支払いは、単なる「出費」ではありません。確定申告で正しく申告すれば、「所得控除」として節税につながります。つまり、支払った保険料が課税対象の所得から差し引かれるのです。
たとえば、以下のような保険料が控除の対象になります:
- 国民健康保険料
- 国民年金保険料
- 国保組合の保険料
これらを「社会保険料控除」として申告することで、所得税や住民税が軽減され、結果的に手取りが増えることもあります。特に、保険料の負担が大きいフリーランスにとっては、確定申告の際に見逃せない節税ポイントです。
社会保険料と節税の関係については、以下の記事でより詳しく解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
(※ここに「フリーランス 節税」に関する内部リンクを設定)
出典:国税庁「社会保険料控除」
まとめ|最適な選択には知識と情報が不可欠
社会保険料の仕組みを知っておけば、突然の負担に驚いたり、不安になったりすることも減らせます。正しく理解することで、保険料を軽くできる制度や、自分に合った選択肢にも気づけるはずです。
フリーランスは、みずから制度を選び、手続きを行う責任がありますが、すべてを一人で抱え込む必要はありません。迷ったときは専門家の力を借りるのもひとつの手です。
「知らなかった」で損をしないように、まずは今日からできることを。情報を味方にして、安心できる働き方を築いていきましょう。