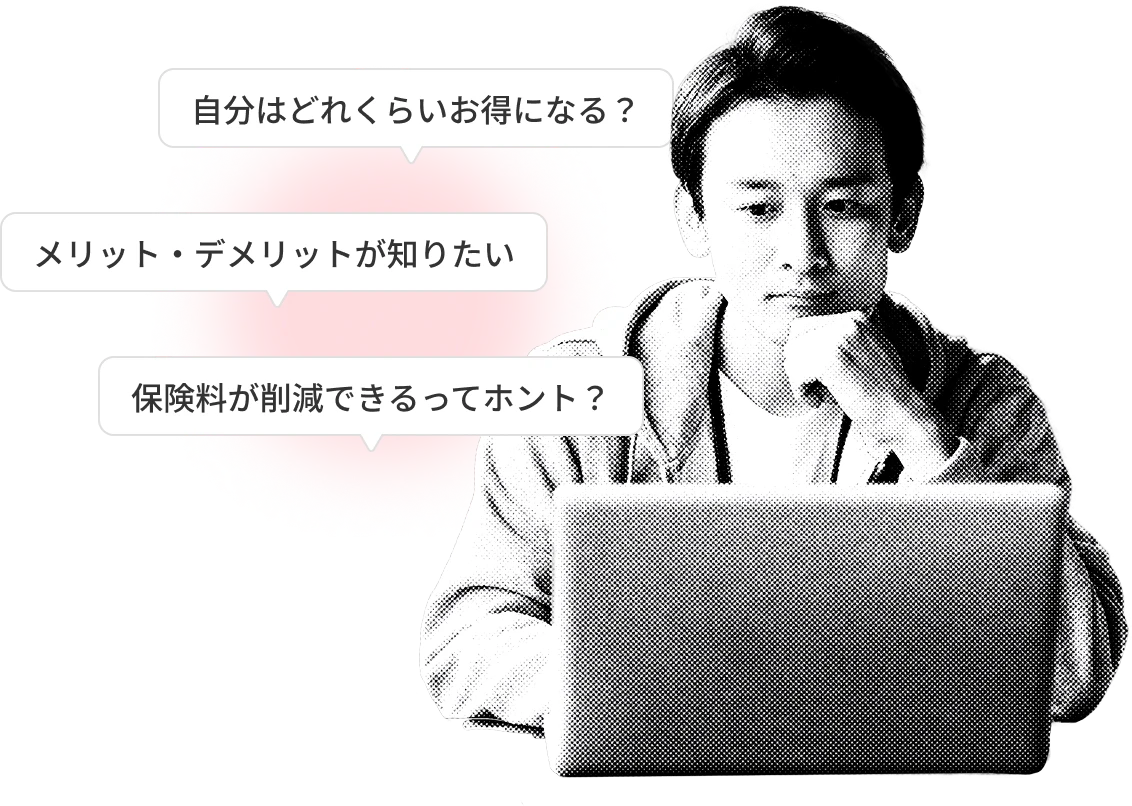- 働き方・キャリア
フリーランスになるには何から始めるべき?未経験から独立するための3ステップ

「フリーランスになりたいけど、何から始めればいいか分からない」と悩んでいませんか?自由な働き方に憧れながらも、収入や将来への不安を抱える人は多くいます。
しかし、会社員やアルバイトのうちから計画的に準備を進めれば、独立後も安定した収入を得やすくなります。本記事では、未経験でも安心して始められるフリーランスの具体的な準備や手順を解説します。開業手続きや資金計画、仕事の取り方まで紹介しますので参考にしてください。
【ステップ1】在職中にやるべき準備を進める
フリーランスを目指すなら、在職中に土台を整えておくことが大切です。独立後の不安を減らし、安心してスタートを切るために、次の準備を進めましょう。
- 自分の強み・スキルを棚卸しする
- 資金計画を立て必要な貯蓄を用意する
- 副業で小さく始めて実績を作る
- 家族の理解を得る
自分の強み・スキルを棚卸しする
フリーランスは「自分という商品」を売る仕事です。まずは自分の得意分野や使える技術を洗い出し、客観的に整理しましょう。例えば「文章が得意」「デザインソフトが扱える」など、どんな小さなスキルも組み合わせれば強みになります。自信がない部分は、資格取得やオンライン講座でスキルを補強すると安心です。
資金計画を立て必要な貯蓄を用意する
独立直後は仕事が軌道に乗るまで時間がかかるため、生活防衛資金を用意しておきましょう。最低でも1〜2か月分、可能であれば6か月分の生活費と事業経費を確保すると安心です。
生活費は家賃・食費・通信費などの日常の支出を含め、事業経費にはソフトウェアやツールの利用料など、事業の継続に必要な費用も忘れず計算しましょう。事前に必要額を算出しておくことで独立後の不安を軽くできます。
副業で小さく始めて実績を作る
いきなり独立するのが不安な人は、本業を続けつつ副業で少しずつ始めるのがおすすめです。週末や夜間の空き時間を使って案件に挑戦すれば、仕事の進め方や納期管理、クライアント対応に慣れると同時に実績も増やせます。
さらに、同業者やクライアントとのつながりも広がり、独立後の安定した仕事につながる人脈づくりにも役立ちます。
家族の理解を得る
フリーランスへの転身は、収入や生活リズムの変化、将来の不透明さから家族に不安を与えがちです。そのため、安心できる根拠を示すことが重要です。
生活費や資金計画、収益の見通しを数字で示しましょう。例えば「1年分の生活費を貯蓄し、副業で月20万円を稼ぎ、複数企業と継続案件を進めている」といった実績を伝えると説得力が増します。
さらに、収入減への備えや支出管理も共有すれば、「計画的に準備している」という安心感が家族に伝わり、協力を得やすくなります。

【ステップ2】退職して開業するまでに必要な手続きを行う
退職したら、次はフリーランスとして開業するための準備です。ここでは、必ず押さえるべき以下の手続きを紹介します。
- 健康保険の選択肢を比較して、自分に合った制度を選ぶ
- 国民年金への切り替え手続きを行う
- 開業届を税務署に提出する
- 青色申告の申請手続きを行う
健康保険の選択肢を比較して、自分に合った制度を選ぶ
雇用先を退職すると、健康保険の選択を自分で行う必要があります。主な選択肢は以下の通りです。
- 国民健康保険:市区町村が運営し、保険料は前年所得に応じて変動
- 任意継続健康保険:退職前の会社の健康保険を最長2年間継続可能
- 家族の扶養に入る:条件を満たせば家族の社会保険に加入でき、保険料負担が不要
- 国民健康保険組合の保険:特定業界に所属している場合に加入できる団体保険
それぞれの特徴や保険料は異なるため、収入やライフプランに合わせて比較検討し、納得のいく制度を選びましょう。
以下の記事では、フリーランスの上記の健康保険について詳しく解説しています。各保険の特徴や加入期限について詳しく知りたい方は、ぜひ本記事とあわせて参考にしてみてください。
関連記事
国民年金への切り替え手続きを行う
雇用先を退職すると厚生年金の資格を失うため、国民年金への切り替えが必要です。手続きは退職日の翌日から14日以内にお住まいの市区町村の役所(または役場)で行ってください。
また、国民年金だけでは将来受け取れる年金額が少なくなる可能性があります。老後資金に不安がある場合は、国民年金基金やiDeCoの活用を検討しましょう。どちらも任意加入でき、掛金が全額所得控除になるため、節税しながら資産形成が可能です。
国民年金基金やiDeCoの仕組み、加入のメリットについては、以下の記事で詳しく解説しています。老後資金の備えに関心のある方は、あわせてご覧ください。
関連記事
フリーランスが得するiDeCo入門|節税と資産形成を両立するコツ
開業届を税務署に提出する
フリーランスとして正式に事業を始める際は、開業届を税務署に提出します。法律上は事業開始から1か月以内に出すことが推奨されています。
提出方法は、税務署窓口・郵送・e-Tax(電子申請)の3つです。e-Taxはオンラインで完結できるため、時間が取れない人にも便利です。国税庁のサイトでは開業届のPDF様式や記入例がダウンロードできるので、事前に確認しておきましょう。
青色申告の申請手続きを行う
フリーランスになったら、開業届と一緒に青色申告承認申請書を提出しましょう。青色申告は帳簿付けなど一定条件を満たすことで最大65万円の所得控除が受けられる制度で、課税所得を減らせるため節税効果が高いのが特徴です。
ただし申請には期限があり、原則は開業日から2か月以内、またはその年の3月15日までに提出が必要です。期限を過ぎるとその年は利用できないため、早めの対応を心がけましょう。
【ステップ3】仕事を獲得するための準備をする
開業手続きが終わったら、次は仕事を取る段階です。ここではフリーランスとして案件を獲得するために知っておきたい以下のポイントを紹介します。
- ポートフォリオを整えて実績をアピールする
- SNSやブログで情報発信する
- クラウドソーシングを活用する
- フリーランス専門エージェントに登録する
ポートフォリオを整えて実績をアピールする
フリーランスとして仕事を得るには、スキルを目に見える形で示すことが大切です。たとえ未経験の分野でも、自主制作の成果物をポートフォリオサイトで公開すれば、実力を伝えられます。例えばデザイナー志望なら、趣味で作ったロゴやWebデザインでも評価対象になります。
実績がない場合は、架空の案件を想定して課題を設定し、企画から納品物まで仕上げてみましょう。ポートフォリオは、クライアントに「安心して任せられる」と思わせる信頼の証となります。
SNSやブログで情報発信する
フリーランスが案件を獲得するには、SNSやブログ発信が効果的です。X、Instagram、LinkedInなどでスキルや制作物を発信すれば、企業担当者や同業者の目に留まりやすくなります。
またブログやポートフォリオサイトで実績や得意分野をまとめれば、オンライン上の名刺や営業ツールとして信頼性を高められます。価値ある情報を定期的に発信し続けることで、蓄積された内容がブランディングや案件獲得につながります。
クラウドソーシングを活用する
フリーランスとして最初の実績を作るなら、クラウドソーシングの活用がおすすめです。クラウドワークスやランサーズなど、大手サービスには未経験者向けの案件も多数あります。
実績が少ない段階では取り組みやすい仕事を選び、コツコツ対応して信頼を積み重ねましょう。報酬は企業との直接契約に比べて低めですが、経験を得る場として有効です。慣れてきたら高単価の直契約や継続案件へと移行し、収入アップとスキルの幅を広げましょう。
フリーランス専門エージェントに登録する
ある程度の経験やスキルを持つ人は、フリーランス専門エージェントへの登録が効果的です。エージェントは企業とフリーランスをつなぎ、スキルや経歴に合った案件を紹介してくれます。
営業や契約交渉が苦手な人でも、エージェントが間に入ってサポートするため安心です。実績が少ない初心者でも、職歴やスキルが評価されれば案件を獲得できる可能性があります。自分で営業するより効率よく仕事を得られ、安定収入を目指す手段としても有効です。
事前に準備を整え、安心してフリーランスを始めよう
初めてのフリーランスへの挑戦には不安がつきものですが、事前の準備と計画でリスクは最小限に抑えられます。本記事で紹介したステップを実践すれば、未経験からでも独立への道筋が見えてくるはずです。
大切なのは「失敗を恐れず、まず一歩を踏み出すこと」です。小さな行動でも積み重ねれば大きな成果につながります。ぜひこの記事を参考に、フリーランスへの新たな挑戦を始めてみてください。